日本のスローフードである郷土料理や伝統食、その根にある在来の風土食材を背景にした食餌療法を意味するミルキーハウス独自の日本の薬膳です。こちらは代表の輿石みゆきが医療及び食農現場に従事し30余年の研究から2000年の時に情報公開した内容を掲載しています。五感で学ぶ健康教育のページと併せてお読み下さい。
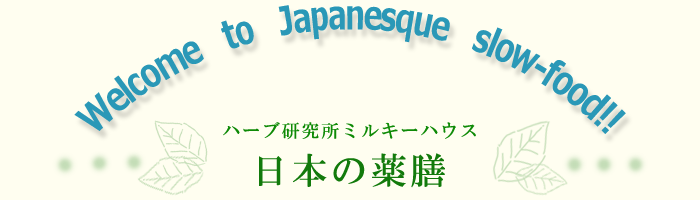
~海と陸に住む美しい生き物たち・・
動植物と共存し合う本来の姿~環境問題に取り組みこれからの未来映像を明るいものに~
長い文化文明の歴史の中で民族の違いや宗教的な風習や偏見もある中、インドのアーユルヴェーダを始めヨーロッパのハーブ学、東洋の中医学等は、豊かな地球の環境資源があってこそ、生まれ育った植物や生き物を薬餌として受け継がれてきた伝統医学療法であり、近代薬学のもとになるものです。 経済産業社会に生きてきた私たちは、自らの手で地球環境を傷めてしまいました。環境汚染による地球温暖化やそれらによる生態系異変、底をついた地球の資源の中で、「健康」を作る食の安全確保は何処へ求めたら良いのか、私たちの心と体への不安障害は膨らむばかりです。
私たちは日本人。元々は草食人種。忘れてはならない日本人のルーツ(刻まれたDNA)を掘り起こす事で、また各国々の人種の体質と有用野菜等産物の食生活を知る事になり、残された資源の中で、私たちは命の延命維持の為に(またその逆の殺生の意味も有)何が有益で有効か研究していく必要があるとミルキーハウスは考えます。 今地球環境崩壊寸前のこの緊迫した時代こそ、地球のターニングポイントとして、また人の体内環境を、外因(体)と内因(心)に当てはめ意識啓蒙し、健やかで豊かな暮らしを一人一人が実践する事を願う、ハーブ研究所ミルキーハウス独自の「薬膳学」になります。
生きる 活きる 行きる=3つの「いきる」
宇宙の創造物と生命の小宇宙の世界。万物には全て陰陽があり、太陽と月、熱と冷の温度変化により、風が起こり陸と海が分かれ、その海の潮の満ち引きには命の誕生の不思議があると言われています。私たちは人間として生まれた限り、地球上の全ての生き物たちと共存共栄しながら、豊かな自然界に在るものを 活かし、生きて、行く 知恵を働かせなければなりません。
- 人は「生きる」為、生命の存続の為に、食べなければなりません。食べ物は、体の中で、物理的、化学的、生物的消化を経て「栄養素」と言う形で吸収されます。
そしてその代謝能力エネルギー量は、人それぞれの健康状態や取り巻く環境状態によって違い、現代栄養学で言うエネルギー数値基準はあくまでも一つの目安であり、個々の生体プログラムを入れない限り確かではありません。
人が動くのに必要な(思考するのも細胞活性エネルギーを必要とします)瞬時エネルギーになる炭水化物、脂質、蛋白質の中の炭水化物一つとっても、その素因は「炭素」と「水素」と「酸素」になります。 野菜にはどんな繊維質の野菜でも、葉脈、茎幹、根茎、それに種子部と各部位によって栄養配分量が違うものの、体に必要な栄養素が充分に含まれていて、単純に私たちが野菜を生で食べると言う行為は、その中にある「栄養素の水」と「酸素」を体の中に入れる事になります。 - 人は「生きる」為に、食べ物を「活かす」知恵をつけました。獣を屠殺して、火を使い焼いたり蒸して燻製にしたり、太陽と風を利用して乾物にしたり、塩で貯蔵したり、家畜の乳や野菜を醗酵させたりと、病気や死の恐怖から逃れる為に、人は長い年月の中で知恵を働かせて命を繋いできました。
そしてお茶の木一つにしても、自生する場所の気候環境によって味や香りが違う事を人々は知り、それぞれの民族の中で楽しむ食文化が生まれました。この先どんな時代が来ようとも無駄のない生活環境作りに、食のみならず衣食住すべてにおいて、残された地球上にある貴重な資源を「活かす」研究を私たちは惜しんではなりません。 - 人は「生きる」為に、また命を永らえる為に、どんな時代が来ても「活かし」ながら生きて「行く」必要があります。家庭と言う小さな集合体から社会の大きな集合体へと、一生係わりながら学習していくことを忘れてはいけません。そしてどんな国に生まれても、死に行き歩む迄、人とふれ合い、またすべての陸や海の植物や生き物たちとふれ合いながら、その社会的な背景の中で、人として生まれてきたことの尊厳をこの地球上で保障されなければなりません。
ヒトの生体構成:元素対比
物質の大元である宇宙の元素は、水素、ヘリウム、酸素、炭素等から創られています。海や地球の表層部の元素を調べると元素対比において人体と海水の10番目迄の占める成分が似ている事がわかります。それは地球内部からマグマが噴出しその鉱物が人も含めて動植物自然界の全ての生命の創造に係わり生き繋ぎ続けていると言えます。生体細胞を構成する約7割の水分、それに係わるミネラル量比重が重要と考えます。生物の生命活動に不可欠なBioelements生元素は、ヒトの場合カリウムは細胞の内側、ナトリウムは細胞の外側、カルシウム、リン、マグネシウム、フッ素は骨組織や歯に分布しています。
 |
 |
 |
|
| 1位 | H水素 | H水素 | O酸素 |
| 2位 | O酸素 | O酸素 | Siケイ素 |
| 3位 | C炭素 | Cl塩素 | H水素 |
| 4位 | N窒素 | Naナトリウム | Alアルミニウム |
| 5位 | Caカルシウム | Mgマグネシウム | Naナトリウム |
| 6位 | Pリン | S硫黄 | Caカルシウム |
| 7位 | S硫黄 | Caカルシウム | Fe鉄 |
| 8位 | Naナトリウム | Kカリウム | Mgマグネシウム |
| 9位 | Kカリウム | C炭素 | Kカリウム |
| 10位 | Cl塩素 | N窒素 | Tiチタン |
| 11位 | Mgマグネシウム |
生体に必要な基本の3要素
- 塩(塩分)
食用の「塩」は本来真っ白です。鉄錆びや泥の汚れが混ざる事により茶褐色等の色の変化が見られます。自然塩、天然塩、ミネラル塩、天日塩の呼び方の他、陸地産の岩塩や製法の違いなど様々ですが海水塩が純度ともに健康に良い塩になります。「塩梅あんばい」と言う言葉どおり塩は料理の味の決め手になるものです。舌で舐めて感じる塩鹹い(からい)味の中にも、銅やマグネシウム含量で違ってくるまろやかな甘みがしますが、素材を柔らかく煮込む時に入れる塩の量とタイミング、素材の身を引き締め、色止めや保存醗酵等用途は色々ですが、塩は塩、ナトリウムNaの意味にしかありません。驚かれるかも知れませんが、野菜に含まれる栄養素量の割合と塩のミネラル量が金属や水と反応して美味いも不味いも決まると言って良いでしょう。塩がトマトのグルタミン酸と化学反応して甘くなる事もそうです。焼き塩にするのか塩をスパイス代わりに使うのか・・鍋素材が違うのか等、まさに調理人と切っても切れない塩の「塩梅」の世界は非科学ではなくサイエンスなのです。
夏は汗とともに体のビタミンミネラルの損失量が多く、そんな時減塩と言う考え方は致命傷です。そうかと言って高血圧症や心臓疾患で療養中の方は摂り過ぎてはいけませんが、人の体は上手くしたもので塩辛い物を摂り過ぎた時は必然的に喉が渇き、水の補給をする事で体内の塩分量を調整し利尿する仕組みになっています。「塩」は生体維持に最も必要な要素で塩分無くしては生きる事ができません。塩分は腎臓を滋養する大切な役目があります。人の体は、血が滞ると癌の原因になりますが、塩分と水分バランスを調整しながら血液と反応し生体の中を循環しているのです。
日本には大豆に塩を入れ麹菌で醗酵させた「味噌」の最高の和食文化があり、味噌で煮込んだ山梨の郷土料理「ほうとう鍋」で戦いに臨んだ甲斐の国の武将「武田信玄公」も塩と縁が深いのです。仏事にも「お清めの塩」として今日まで使われ、日本の代表するスポーツ相撲においても、土俵を神聖な場所としてお相撲さんが塩を撒く儀式を行っています。その他聖書の中にも「あなた方は地の塩である」と教えが記される等、「塩」は生きる上で体に必要な海からの贈り物と言うだけでは無くして、私たちの想像をはるかに超えた宇宙のメカニズムの中でもっと意味深いものがあるのかも知れません。
- 野菜とその栄養素水
元々草食人種だった腸の長い日本人にとって、地層的に多い日本の水、軟水は、腸に優しく消化吸収を助けます。また火山国の日本はその恩恵で温泉が豊富で、泉質によって含有成分が違いますが、皮膚吸収と併せて温泉を飲用水として糖尿病や免疫代謝等の治療目的に利用されています。食べ物の消化形態で一番手っ取り早く滋養できるのは飲用する事、つまりお茶やスープになります。日本のお茶もビタミンCカテキン効果等と近年やっと話題になりましたが、何故日本ではハーブティーやら薬膳茶的所見なるものが遅れたのかと申し上げますと、単純に日本の水が当たり前のように安全で美味しかったからです。中国や西洋の各国々を巡ってみても大概真水として飲むには水質に問題があり、働き好きな日本人と違って良くお茶を飲む習慣(その逆の考えで質素に食事回数を減らす為とも言われている)があり、水にハーブや生薬を入れて煮出す事の方が真水より安全で癒しと健康効果を期待する為の今の茶文化が確立したと言えます。
ここで生体に必要な要素が「日本の水」と言うのではありません。異常気象と温暖化、産業排水や農薬汚染、化学肥料による微生物の壊死から生きた土が無くなり地質学的にも環境的にも現状のままでは、近い時期に世界の食糧難民生活が必ず来ると言っても過言でありません。そんな懸念される環境の中で、日本のおいしい水の確保は残念ながら到底望めそうにありません。
土壌を還しゼロ地点になって、農(物づくり・・昔は農そのものを言いました)に帰る事こそミルキーハウスの望みであります。そして色々な観点から薬餌と言う方向で考えると、病気にならないように農山漁村の環境的にも安全な元素含量土壌下で育つ米や野菜を始めとする食糧自給を考え生命活動(生活)する事です。
私たちが踏みしめるこの大地に眼を向けると、あらゆる化合物と一体となって発現する地表の鉱物、ミネラル元素の存在があります。大陸や海を覆い地熱や太陽の光エネルギーとなって散在、また全ての生物の生体内にも存在している素因子です。ミネラルは生物の行動情報においてそのエネルギー代謝に係る最も重要な位置づけになる成分と言えるものです。それと同時に私たちヒトも含め生物にはヒ素や鉛、水銀などの有害毒素(今世の位置付け)も持ち合わせて生命維持をしています。それは子孫を残す必要から植物種子に毒を持つ意味と同じなのか、生体免疫の為に始めから存在しているのか、科学者たちの視点はそこではないので現時点では分かりませんが(入門編を参考)、いずれにしても行動情報によるエネルギーとして海に生きるものは海の草や浮遊物等のミネラルを、また陸に生きる私たちは地表の成分を吸い上げた、大地に生え育つ木々や植物から摂取する必要があります。巨大な陸の動物たちも、また固い甲羅をもつ海川の貝や海老たちも皆太陽光から育つ野菜と同じ緑葉植物(葉緑素)を食べて生きています。私たちが摂取した野菜中のミネラルは生体内で化学変化を起しそれがいわゆる酵素作用に係るものですが、タンパク質や脂質、糖質等の主要エネルギーに比べると微量ではあるものの生体活性の為の無くてはならない栄養素です。
簡単にまとめると、生体に必要な2つ目の要素は、体のもとを作り代謝に係る有益で有効かつ薬理的な栄養素(カルシウム、鉄、カリウム、マグネシウム等のミネラルや代謝機能に係るビタミン)を野菜から常時摂取し生体細胞のバランスを維持する事であり、細胞の劣化つまり単純に老化予防対策として細胞に浸潤しうる野菜の栄養素的な水分(生食、加熱食に係らずこちらでは栄養素水と言う)も必要としています。土の中で育つ野菜は体の滋養が必要な時に極力食べるようにし、土の上に育つ葉っぱや種子花の香りも含めた野菜は、免疫系、ホルモン系、神経系が崩れて疲れている時に、食欲中枢をリセットする意味でも五感を癒す野菜と考えて摂取するようにして下さい。
犬や猫達が闇雲に青く伸びた雑草を食べたがるのは何故でしょう。彼らは獣の体の毛についたゴミやホコリを舌で舐めて、胃の中に溜まってしまった雑菌物を草と一緒に吐き出したり下痢を起こす事で、解毒する事が必然的に出来ているのです。健康でいる為に体のバランス調整をすると言う事は、食事をして養分で「滋養」するのか、過剰摂取した養分を意味のある食材を使って「解毒排泄」するかの判断を行い適切な食事療法をすると言う事です。具体的には、栄養豊富な旬野菜を優先し、食材の薬効を充分引き出しながらハーブやスパイスを有効活用し、野菜の「苦味」には内臓機能の炎症や解毒作用等その薬理効果があると考えた上で、野菜や果物の自然な甘みの糖分と合わせ調味し、そして温性野菜と冷性野菜の考えは素材の下処理や調理の仕方次第で如何様にもなると言うミルキーハウスの薬膳調理理論です。
温暖化とともに日本の四季野菜も薄れ、西洋の植物ハーブも中国の生薬(動植物野菜や鉱物)も生態系が崩れてきている中、病院や施設学校等の集団調理現場を始め人々の口に入る食材の安心安全な野菜の確保がこれからの課題になります。そして今後たとえ水田が枯れ果て水稲が作れなくなっても、地球上どこでも栽培可能な主食にもなり得る完全食材に近い野菜をあえて挙げるとジャガ芋やサツマ芋等の芋類になります。
- 油(油分)
弱肉強食の動物の世界では、敵から身を守る為に最低必要量の餌だけ食べ何日も放浪することができますが、それは生命を維持する貯蔵エネルギーとなる脂肪を摂取しておくからです。体内にある脂質と呼ばれるもの、そのほとんどが中性脂肪(単純に脂肪と言う)になります。聞き慣れたコレステロールは炭水化物や脂質から作られ、体を作る大切なものになります。脂肪は確かに肥満を忌み嫌うダメージ的な言葉のような気もしますが、脂肪(油分)は塩分や水分を体中に潤滑させるエネルギーを持つ生体を維持するのに必要な3つ目の要素です。
どんな食事でも「腹八分目」と言う言葉があるように、食べ過ぎる事は体の酸化指数を増し細胞の老化を引き起こし、胃が膨らむばかりで思考力も劣るので余り理想的な食べ方と言えません。必要な脂肪と言え余分な脂肪分は血管を細くし動脈硬化を起こしやすくします。地球上の油脂は動植物水陸両生にありますが、食用肉や漁獲量の確保には限度があります。植物から採れる各国の主な食用油脂を並べると、米、大豆、オリーブ、菜種、とうもろこし、パーム、サフラワー、アーモンド、ピーナッツ、グレープシード、ココナッツ等あります。油の酸化ほど怖いものはありません。使い古した油を摂取すると中毒を起こします。これだけ多くの油脂食品と情報の中で体に無くてはならない油分ですが、体質に合った品質の確かな油脂を自身で選択する事です。
近年健康志向も高まり、体に良い不飽和脂肪酸(善玉菌を増やしコレステロールの生成を抑える)のオレイン酸のオリーブオイルやノンカロリーの葡萄のグレープシードオイルなどは需要が伸びてきています。葡萄の栽培種が温暖化とともに変わりつつあるようですが、アフリカの熱帯地帯でも美味しいワインが作られ身近に飲めるようになりました。これからは砂漠化してくる土地に環境緑化の為の植林を行う事が必要になり、葡萄の木にしても、ワイン用と種子から採れる油脂用と有効活用すれば廃棄の問題も少なくてすみます。食だけでなく工業油脂も食用油脂と並行してこれからの地球環境資源対策を考えて行かなければなりません。
自然界の酸素、水素、炭素は不可欠です。それに加え、・N窒素=茎や葉を育てる・Pリン=果物や花づくりに必要な養分・Kカリウム=根を伸ばし球根を太らせる、この3つが作物に必要な最低条件の3要素です。その他Caカルシウム、Sイオウ、Mgマグネシウム、Mnマンガン、Fe鉄、Bホウ素など微量要素を加えると全部で16種類の要素が野菜に必要となります。土が変われば野菜の姿形も変わるように、土地環境による成分数値の違いがそのままの野菜の個性、特色となる訳ですがそれを食事療法に活かすようにします。大々的に農事に携わらなくても野菜を育てる事は命を育てて命を頂く大切な「生きる」事、食育にも繋がります。始めは耐性や害虫駆除などもあり自給自足の真似事のようでも、季節を通して育てると色々なサプライズに出会え、農に学ぶ事は心も豊かにしてくれます。
また料理人にとって大切な野菜の個性である味、香り、色についてですが、特にタンパク質を構成するアミノ酸量と水分量により野菜の美味しさの基準が変わる事が分かっています。香りはアスパラギン酸、野菜の色はロイシン、アスパラギン酸、プロリンが係っています。一般に苦土と言われている葉緑素に必要なMgマグネシウム、それに加えて土の酸性を穏やかにする石灰=Caカルシウムが作物の生育に必要です。太陽光と雨水のバランスを見る為にもお天気日誌を付けると良いでしょう。
野菜を含めこの地球上にある全ての植物たちの大切な役目、それは太陽の光を浴びて光合成を行う事です。植物体の殆どが酸素、水素、炭素を占めている事から光合成による葉緑素を作る為に植物は「生きている」と言えます。葉緑素、つまりクロロフィルはヒトの生体細胞に限りなくエネルギーを作り出す生理活性物質※であり、野菜を始め海藻類に多く含まれ私たちの健康維持に欠かすことが出来ません。また自然界のあらゆる小さな微生物や菌性たちが行う、炭酸同化作用(一般に言う光合成)の作用も生物生態環境に於いて大事な役目です。微生物(ウィルスを含む)とはそもそも多様な生き物であり、その速攻性、増殖性は生き物たちにとって有用ばかりか生と死を分ける病原性になる破壊的威力を持ちます。菌による腐敗と発酵は同じ意味であり有用菌を食品に扱います。海洋生物に無くてはならないプランクトンは太古からの微生物です。地球上の全ての微生物はその有機物の分解を無機調整しています。そのお蔭で私たちも水も空気も浄化された環境で生きる事ができる、そう思うとこれからの地球化学循環環境への意識に繋がると考えます。
| ※生理活性物質… | 生物の生理行動において特定な作用や調整機能を起す性質のある化学物質の事を言います。 免疫強化、老化予防、酵素やホルモン系に係り代謝を良くする・・ビタミン、ミネラル、核酸、酵素等。 代謝機能に係わる細胞内のタンパク質は栄養素外の機能として生体の恒常性(ホメオスターシス)に必須で細胞組織オート ファジーの仕組み等も講座にて説明しています。 |

農耕民族日本人のDNA主食=五穀(稲・麦・粟・大豆・小豆)
十穀(籾・大豆・小豆・蕎麦・大麦・小麦・稗・粟・黍・胡麻)
日本人による日本人の為の健康にイ(^―^)イ食べ物
常備的に利用できる!滋養健康効果がある!生活習慣病予防に活かすことができる!
| アブラナ科の特徴 カリウム、カルシウム、ビタミン類、葉緑素を多く含む野菜が多い |
抗菌性、抗酸化作用が強いので癌予防及び癌細胞によるDNA損傷を予防する、コレステロール値低下、閉経後の乳癌予防、性ホルモン分泌促進作用、脳出血や高血圧症予防、その他糖尿病等生活習慣病の改善となる生体機能調整を行う | 小松菜、高菜、野沢菜等の菜の花類・キャベツ(芽キャベツ含む)・カブ・ブロッコリー・ワサビ等 特にこの科目のスプラウト類 |
| マメ科の特徴 炭水化物、タンパク質、他ミネラル成分がバランス良く繊維質も多い |
脳活性、肥満症改善、肝機能の強化、肺癌リスク低下、ストレス緩和作用、動脈硬化予防 | 小豆、落花生、空豆、エンドウ豆、インゲン豆、緑豆 |
| ヤマノイモ科の特徴 亜鉛 マグネシウム デンプン分解酵素(アミラーゼ) |
糖尿病改善、滋養強壮作用、胃腸と腸内粘膜の強化 ホルモン等生殖器の機能を高める、肥満症改善 | 山芋類(長芋、大和芋、つくね芋)、大薯 | ||
| サトイモ科の特徴 カリウム、アミノ酸、 ガラクタン等消化酵素 |
糖尿病予防、腎機能向上、肝機能改善、 高血圧症や動脈硬化改善、脳活性、認知症予防、 コレステロール低下作用 | コンニャク芋 |
山の芋に対し里の芋とは・・古来縄文時代から食されていたとされる里芋を言い、日本人のDNA体質に係わる歴史上の元祖「芋」はこの里芋であることを忘れてはならない。東南アジア系のタロイモと同種。里芋のぬめり成分やガラクタン物質が胃潰瘍などの胃腸粘膜保護、コレステロール低下作用となる。里芋にあるミネラル元素のMoモリブデンは、人の肝臓や腎臓臓器内にあり代謝や酵素作用に係っている物質である。微量摂取と言え病後等栄養が必要な時は、植物性のみならず動物性のタンパク類レバー類にも含まれているので薦める。里芋の形状は筍や海老のような形の京芋、山梨の八幡芋に代表される親芋と子が塊の形状となる八つ頭芋等形が色々ある。弘法大師の逸話として出てくる石芋は「食わず芋」毒性の里芋と思われるが、野に生え葉の形等似ているがシュウ酸カルシウムの毒性野草で中毒となるので気を付けるようにする。同科目のコンニャク芋は周知のとおりグリコマンナン食物繊維であるのでコレステロールを抑え肥満症対策に良い。ズイキと呼ばれる里芋やハス芋の葉柄部分はそのまま野菜として利用したり、乾物にして利用すると良い。動脈硬化、糖尿病予防食になる。
| ハス科の特徴 デンプンが主体、ビタミンB1、B2、C、B12、アスパラギン、アルギニン、チロシン等 |
胃潰瘍時の胃腸粘膜保護作用、動脈硬化予防、 糖尿病改善、腸カタルや大腸癌予防 | ジュンサイ:芽を食用(近年ハス科あるいはスイレン科分類からハゴロモモ科と変わったが、多年生の水生植物、同類学の野菜としてこちらに置いた) |
| キク科の特徴 鉄分、カルシウム、ビタミンE、食物繊維、イヌリン |
癌予防、高血圧症、腎臓機能向上、血液浄化、肥満症改善、大腸癌予防、動脈硬化予防、性ホルモン分泌促進 | 蕗(ツワブキ含む)、菊類(春菊、菊芋、菊苦菜別名チコリー)、レタス、サラダ菜、ヤーコン、ステビア(近年の外来種であるが抗癌、抗ウイルスに期待される為特記) |
| セリ科の特徴 ビタミン類、カリウム、根にβカロテンが多い、食物繊維 |
粘膜強化保護作用、抗菌、抗酸化作用、癌予防、糖尿病予防、高血圧予防、鎮静作用 | セロリー、パセリー、明日葉、三つ葉、セリ、シシウド、ハマボウフウ |
| ナス科の特徴 糖質、ビタミン類 |
抗酸化作用、高血圧症予防 | トマト、じゃが芋、ピーマン、唐辛子 |
| ウリ科の特徴 ビタミンAを始めとするビタミン類が豊富、カルシウム、鉄分、リン |
糖尿病予防、冷え性対策、動脈硬化緩和、胃潰瘍等胃腸粘膜保護作用 | 胡瓜、ゴーヤー、西瓜、沖縄琉球冬瓜 |
| アオイ科の特徴 ビタミンA、C、E、B1、B2、カルシウム |
癌予防、高脂血症予防、血糖値降下作用、胃腸粘膜強化、整腸作用、ウィルス等抗菌作用、抗酸化作用による老化防止、認知症予防 | オカノリ(原種は本葵) あと近年の分類体系変動により外来種モロヘイヤを置く |
| アカザ科の特徴 カルシウム、マグネシウム、鉄分、カリウム |
貧血予防、抗酸化作用、気管支炎緩和作用 | 陸ヒジキ、甜菜(てんさい) |
| ユリ科の特徴 タンパク質、ビタミンC、B1、B2、カルシウム、リン、鉄分 |
抗癌作用、動脈硬化予防、血栓予防、気管支喘息の緩和、強壮作用、生体機能調整、 ※高血圧時食すのは禁止とする | 葱類、玉ねぎ類、ラッキョウ、アスパラガス、ニラ |
◆生体活性、生活習慣病予防に欠かせない木の実(果物)は日本のスローフード食材「山梨の八珍果」の中に!!
1.葡萄 2.桃 3.りんご 4.梨 5.柿 6.栗 7.ザクロ 8.クルミ(または銀杏も言う)は山梨を代表する果物である。
生まれ育った場所あるいは生活している場所に生え育ち採れたものを食べる「身土不二」と言う考えは元々仏教から来た用語であるが、地域生産農産物の「地産地消」の言葉と一緒に良く使われる食養論の考え方である。日本を代表する昔からの果物と言えばどこの民家にもある柿の木の実であり、軒下に吊るす枯露柿の様子は残したい農村の風物詩スローフードである。柿が今世の生活習慣病予防になる抗酸化作用で癌予防となる。またリンゴも古くから慣れ親しんでいる果物であるが、西洋ハーブで言えばバラ科、血液浄化に係り糖尿病予防となる。果物は完熟果を食す事、ジャムやコンポートにしたものを常備し生活習慣予防の治療食に砂糖の代用で使うと良い。また醸造のワインや酢(柿酢・りんご酢・ザクロ酢等)、薬用酒(ザクロ酒)、乾物(干し葡萄、干しクルミ、枯露柿)等色々食材利用し生体活性を図る。クルミ(銀杏も含めて)はビタミンEが豊富で土中に実る落花生と同じ動脈硬化や老化防止に良い。クルミのシワが脳ミソに似ている事から脳に効くと昔から言われるとおり血流が脳まで届く健脳食であり精神安定を促す食材でもある。ここで注意点を記す。バナナは手軽な完全食としておやつにもダイエット食にも日本人に歓迎された日常的な果物であるが、果物と言え日本人のDNA体質から外れる南洋系のパパイヤ、マンゴー、キウイ等の強い酵素を持つ果物は細胞活性に役に立たないと考える。特にマンゴーは接触性皮膚炎単純にかぶれを起すウルシ科植物であり、反応が出た場合アナフィラキシーショック症状を起こし喉が腫れ呼吸困難等の事故が多いので耐性がない幼児期に食すのを回避して頂きたい。体質に合えば何ら問題がないが、後先になったが身土不二の例とした。八珍果の意味は、8つの珍しい果物ではなく健康に役立つ8つの珍重されるべき果物、今世での生活習慣予防対策に必須の栄養群であり、山梨はその他にも種類の多い肝機能改善のスモモ、鉄分が多く冷え性に良いサクランボ、ビタミンCの多いイチゴ、血糖値上昇を抑えるイチジク等多彩な免疫代謝に係わる果物が沢山栽培され、まさに健康長寿を目指すフルーツ大国山梨と言える。
未病予防の健康的な薬味スパイス

ローズマリー、ラベンダー、バラ、ジャスミン・・甘くもスパイシーな香りのハーブたち。西洋の香り文化の一つであり薬草成分をアロマ医療分野に使う。生活雑貨のポットポプリーが始めて日本に入った頃からハーブは園芸とキッチン分野に広がり今に至っている。アロマの世界は身近な茶道や香道の和文化にも溶け込んでいる。キッチン用ではイタリアンに欠かせないバジルや薄荷飴でお馴染みのミント等シソ科ミント系は定着したものの、インドカレーに欠かせないカルダモン、コリアンダーやクミン等のシード(種実)スパイス、またタイやベトナム料理に使うパクチー等の生ハーブ野菜等は、うどんの薬味やふりかけのように簡単に使いなれない人も多い。日本の欧米食流行りでファミレス等外食産業が寄与した所は大きかったが、日本の和食が見直された今日、その健康食の素になる食材を見直す事が必要となった。昆布や鰹出汁の日本の味の「旨味」ベースに繊細な旬の香りを盛り込んだ和食に、香りの強い西洋ハーブを加えた料理は元祖おふくろの味からは程遠い。一言で言えば元々野菜食、砂糖と醤油味の日本人にとって、肉の臭み消し等強い香りの調理法がこれまでは必要無かったと言える。
そもそもハーブは薬用植物を意味し薬理作用を期待するもの、単に薬草と言う。薬草は自然に生える雑草種様のものだからミネラルを有する土の成分であれば、平地、沼、川や海の沿岸、岩、砂地等雑草的に何処でも強く育つ類のものである。その多くは植物の部位によって薬理作用が違う。日本では先駆けのハーブ愛好家仲間たちからhealthy、eat、relax、beauty、それにsatisfyをつけ加え、動詞形容詞も関係なくして、健康的に、食べられ、リラックスでき、美しく、満足できる..でそのままHERB(S)としたのを覚えている。東洋の漢方薬になる生薬を含めると、生薬は石膏のような鉱物もあれば牡蠣の貝、熊の胆や燕の巣等生物等含まれるので生薬の中の植物分野だけがそれに当たる。TV収録時等では「薬味調味料」としての位置付けから紹介するようにし、また分かり易いよう生野菜としてのフレッシュハーブ、辛味の強いスパイシースパイス、種実のシードスパイスの3つの分類枠はあくまでも近年の組織グルーブの視点が大きいと付け加えさせて頂いていた。
そこでもう少し間口を広くし時代のニーズに合わせ厚生省が発信する生活習慣病予防に意識を向け日本人の為の薬膳食のカテゴリーに近づけ発信するよう、ハーブと同じく語呂合わせらしきものを考えてみた。Special Preventive - Illness Celestial Eatable!!特別な、病気予防に、素晴らしい、食べられる!とそのままの感じではあるが、この上ない極上の意味celestialは政治家ヴィクトルユーゴーのLove is portion・・の詩に出てくる言葉、ハーブは自然が与えてくれた特別な贈り物・・のイメージとしたい。日本でもその昔聖武天皇の身体を心配した皇后が当時中国や東南アジアの国々から取り寄せたとされる約60種類の生薬(植物、鉱物、生物含む)が奈良の正倉院「種々薬帳」に記載され、実際の物も保管されている。「病に苦しむ人々の為に必要に応じ薬物を、万病の如く除かれ千苦全てが救われ夭折する事がないように」と皇后様の思いも記されている。 「生きる」その原点である食と健康その為の農づくり上記リストアップした野菜の他、私たち日本人の身近な食べ物から特に薬理作用のある食材も含めて「薬味スパイスYAUMI-SPICE」と称しミルキーハウスから発信する。
ハーブやスパイス及び生薬と言ったそれぞれの分野をまとめて薬膳と言う健康食のカテゴリーに入れるには、日本人が和食で刺身等の生魚を食べる時の解毒作用的なタデや紫蘇またネギや生姜等ツマとして使う「薬味」と言う領域からの方が方向づけがし易い。美味しい水から瑞々しい野菜が育つ事に加えて種類が多い日本の野菜市場であるが、その中から特に薬理作用が優れている薬味的食材を言う。両極端でなければ色々と筋変えする事が必要であるが、西洋、東洋ともに薬草ハーブの歴史はここ最近のマニュアルの世界ではなく奥深い民間に使い伝えられてきた伝統医学である。一番の大切な事は個々の症例事情(ここでは主に生活習慣病対策とする)を理解し、体質に合わない物は返って体調を悪くする。また何度も触れるがハーブは薬草であり毒にもなりうる雑草ハーブと言う理解、それと長期、多飲、多量はするべからず・・ミルキーハウスの約束事である。アレルギーや難病罹患のある場合は体質改善も必要であるが、社会ストレス等もあり、如何に健やかに暮らせる環境を整えるかと言う基本の事が大切になってくる。健康的な五感教育としてこれからの福祉の問題もあり未病予防の実践に当てはめられるよう患者や医療の症例データも参考に流動的に提案していく。
日本人の為のお薦め薬味スパイス(Yakumi-Spice) 一部紹介!
生活習慣病予防対策の「薬味スパイス」とは、風味、香り、色味成分に特徴があり、食欲増進、抗酸化作用、消化促進、健胃作用、冷え症等の血行不良改善と言った体質改善に欠かせない要素があり、その後の健康維持を期待する食材そのものを言います。江戸時代頃から西洋の物も入ってきてはいますが、一般に言われるハーブ、スパイス、生薬と言われている世界から、特に日本人体質に慣れ親しんでいる物を一部紹介しています。薬効等各詳細説明は文字量の関係で最低量とし省略。※印は商品名。海苔やゆかりは農産海産物商品。尚ニンニクは農作り推薦野菜の為トップ11に記載となります。
| 葱 negi 血圧上昇抑制 抗酸化力高い ビタミン、ミネラルの薬効期待値は白い軟白部分より葉の方が高数値 |
生姜 syoga 抗菌作用、消炎作用、血行改善、ニンニク葱に並ぶあらゆる薬効がある食材 |
茗荷 myoga 血液浄化、αピネンによる高揚作用、生姜科類似作用 茗荷タケ:茎を柔らかく育てたもの |
菊 kiku 茎葉使用=春菊 花使用=食用菊 抗酸化力が高い 体内の毒物を排除する作用(グルタチオン産生効果による) |
蓼 tade 葉を食用 刺し身ツマ用に青タデ、紅タデがある ※タデ酢=鮎の塩焼きに欠かせない 血管強化、痛風時の緩和、他忌虫作用 |
山葵 wasabi 抗菌性、抗癌、血栓予防等血行改善、胃腸障害改善、他忌虫作用、薬効は生食のみ |
鷹の爪 takanotume 辛味成分カプサイシンは全唐辛子にある成分 抗菌、抗酸化作用、消化促進、 肥満型には体脂肪燃焼に適度な運動を加え薦める |
浜防風 hamabofu セリ科 江戸時代より季節のあしらい刺し身のツマとして使用 名には風(風邪)を防ぐ意味が当てられている 抗菌作用 |
ニクヅク nikuzuku 別名ナツメグ 抗酸化作用が強い、頭痛緩和、整腸作用 一度に大量摂取は幻覚に似た症状になるので注意する |
| 日本蒲公英 tampopo 春先の花を干して冷え性に。 |
甲斐芋 kaiimo 明和から作られた日本のルーツ芋、胃弱に。 |
和多々比 matatabi マタタビの虫えいは強壮剤に利用可。 |
公魚 wakasagi 地域により呼称が違うが貴重な蛋白源、ビタミンAが多い。 |
月桃 getto 沖縄に自生、種に健胃整腸作用。 |
桜海老 sakuraebi 春秋の漁獲。駿河の希少なスロー食材。 |
野萱草 nokanzo 春の山菜の金針菜、蕾は解熱に利用可。 |
ウコギ ukogi 平安時代から利用の山菜。樹皮、新芽利用可。 |
麩 fu 千利休の茶時からのグルテンと米粉の元は菓子。食欲不振時に。 |
| 大葉 ohba 日本人に欠かせない薬味、紫蘇の実は栄養価が高く油もオメガ3脂肪酸含有 ※ゆかり=梅漬け後の赤紫蘇をふりかけにした物 |
トンブリ tonburi ホウキギの種 別名畑の肉、高エネルギー 疲労時の強壮作用 |
ジュンサイ junsai 葉緑素による血液浄化作用 |
菱 hisi 実を食用 健胃、滋養強壮、他抗癌作用 |
ニッキnikki 別名シナモン ※八つ橋、ニッキ飴 癌予防、血行を良くする |
麻 asa 実を七味唐辛子に使用 血中における悪玉コレステロール値の低下作用が認められている アルツハイマー型認知症予防 |
☆お薦め 紅葉下ろし 唐辛子と大根の下ろしを薬味として利用 |
山椒 sansyo 実と葉(木の芽)使用 抗菌性、胃腸病の改善と健胃作用 |
銀杏 ginnan イチョウの実・葉を利用 脳腫瘍等に係る脳や末梢血管の改善 肺機能、気管支の強化 |
| 辛子karashi 辛子菜等の種子 昔からおでん等に使う 辛子菜の種の油を搾った後撹拌し乾燥させて作る製法 西洋辛子(マスタード)は種がコショウとなる |
※海苔 nori 海藻類は海の草ハーブ ヨード類ヨウ素は 基礎代謝向上 皮膚粘膜保護作用により病気への抵抗をつける |
胡麻 goma 大豆に並び栄養価が最高値 外皮が固い為擂り潰し利用 |
胡椒 kosho 世界を代表するスパイスの一つ、日本での使用も古い 健胃作用、血行改善 減塩対象者はコショウの辛さで味を変化させると良い |
梅 ume
クエン酸を主に有機酸類が抗菌作用他肝機能活性等疲労回復の万能薬 ※梅干し ※梅肉エキス  |
クチナシ kutinashi 実を利用 糖尿病改善 ※たくあん漬けの色付けに使用 |
桜 sakura 花・葉を食用 血液浄化作用、血行改善 |
※きな粉 kinako 大豆をひき割り粉状にしたもの ふりかけとして普段使いすると良い |
蕗 fuki ※フキ味噌 苦み成分に薬効あり 抗酸化作用、肝機能強化、発癌物質等の毒素排出、健胃作用、痰や咳を鎮める |
貝割れ大根 抗酸化力高い |
茶 cha 日本のカテキン 葉の粉末使用をお薦めする |
みかんmikan 果実を食用・皮を漬物等に利用 |
胡桃 kurumi 野生種の鬼胡桃は滋養効果が特に高い 心疾患予防 抗酸化作用(オメガ3脂肪酸) |
オランダ芹 oranda-seri 別名パセリ 腎疾患、癌予防 鉄分が多いので常食すると良い |
日本蜂蜜 hatimitu 蜜源植物のクローバー共に強壮作用がある 乳児はボツリヌス菌回避の為禁止 |
芹 seri 癌予防、糖尿病予防、高血圧症改善 上記トップ11の大根を参照 |
ウイキョウ uikyo 別名フェンネル 血行促進、ホルモン様のものなので女性の体調管理に良い |
ニラ nira 強壮作用、整腸作用、冷え性改善 |
| 百合 yuri 縄文時から根を食用=日本の山百合 グルコマンナン:糖尿病予防、コレステロール低下 |
栃(とち) toti 実を食用 糖尿病予防、血糖値上昇抑制効果 ※栃餅(とちもち) |
リンゴ ringo 糖尿病予防。不溶性食物繊維のリグニンが癌やコレステロールに効果を発揮する |
☆お薦め リンゴ(リンゴ酸)の擂りおろしや、ペクチンによる胃腸粘膜保護メニューを用いると良い |
棗 natume 昔から日本で庭木としている 実は果実酒や蜂蜜漬けにし常食を薦める 口腔~咽頭~肺癌処方薬に使われている |
☆お薦め ※削り鰹 kezurikatuo ダイエット効果:アミノ酸ペプチドによる 骨を強化する:リン・鉄・マグネシウム含有量多い |
ウコン ukon 食用秋ウコン 薬用春ウコン 胆汁の分泌を促す 成分となるクルクミンに抗酸化作用がある 肝機能強化 春ウコンは特に抗酸化力が強い |
柑橘類 ①類柚子yuzu ②類レモンremon ③類その他の柑橘類(酢橘sudati カボスkabosu他) 調理上枠別とする |
グミ gumi 実を食用 ビタミンE量がトップ トマトと同じリコピン量が多い 抗酸化作用 |
| 土筆(ツクシ) tukushi カルシウム、ゲルマニウム含有 骨粗鬆症、免疫調整、強壮作用のスギナ葉もお薦め |
サフラン safuran 血行改善特に婦人病等通経に良い |
丁子 choji 別名クローブ フトモモ科の蕾を利用 抗ウィルス・抗菌作用 冷え症改善 |
日本薄荷 hakka 一般のミント類と同じ 消化促進、発汗 治療食時等のストレス回避に |
クレソンkureson 血液浄化作用 鉄分含量多い |
桑 kuwa 葉・茎根を薬用 実はブルーベリーアントシアニンの約3~4倍量ある |
庭梅 niwaume 果実を薬酒にお薦め 血行促進 |
三つ葉mituba 動脈硬化等血行障害に効く オランダ三つ葉 =セリ科セロリー |
ケシ keshi 実を食用 カルシウム、モリブデン等ミネラル含有量多い |
| 蓬(ヨモギ)yomogi 発癌抑制のインターフェロンの成分を持つ 造血作用、腎臓、心臓、肝臓等各臓器の活性作用 |
柿 kaki 実・葉を利用 抗酸化作用 ※柿酢 ※枯露柿 |
食事を摂る時に薬味スパイスになる物を一緒に利用することにより、食材の栄養価以上のエネルギーが吸収されます。それは私たちの体の中にある「獲得免疫」と「自然免疫」(=簡単に説明するとマクロファージや白血球等の免疫細胞が何らかのウィルスが侵入した場合、抗体免疫を作って攻撃する、もう一つは免疫細胞自身が異物を食べて分解処理する<食作用>)この2つの防御機能の免疫代謝を強化する事に活かされ、ウィルスや様々な細菌から遠ざける体づくりへと向かう事ができるのです。普段の食事が大切であり、それにちょっと加える薬味、活かさない手はありません。日本人の食生活データをまとめここに一部掲載しましたが、それでも体質に合わないと思ったものはあえて取らないようにしてください。その他、植物野菜の乳酸菌や酵母が共生している発酵食品等は大いに利用し体の基礎土台をしっかりと作る事をお薦めします。免疫代謝づくりは細胞を若返えらせ各器官へ栄養を届ける血の道を良くする事です。その上でミルキーハウスの薬膳調理理論に入るように致します。 | ||||||
|
||||||||||||
 |
||||||||||||
Food and Nutrition Education & Promote Japanesque Slow-Food |
||||||||||||
日本の風土野菜の特徴!
① 在来野菜果菜含め地形気候を活かし種類の多さ世界一!
② みずみずしく消化にも薬効にも優れているものが多い!!
③ 調理の幅が広く乾物や発酵保存利用できるものが多い!!!
大地、光、風、水・・と遊ぶ!伸び伸びとした心と体、五感的要素は自然の中から生まれます
鉱物である石から発光した「火」の発見は人類の歴史を大きく変え土器の発掘からも縄文時代には人間的な生活様式が営まれていました。調理の煮炊きから始まり、風呂を焚く、線香や護摩を焚く、また人の終においても今も変わらず火を使います。電気と違い火は原始的な動力、風力や太陽光と同じ自然利用の環境に優しいエネルギーです。炎をあげる火は私たちのDNAに染みついている五感そのものであり、焚き木や炭の焦げ付いた煙の匂いに人は懐かしくも癒されます。それは私たち人間が火の偉力を心に刻んでいて抗いきれない感覚器官、内因的要素の一つと言えます。
☆☆☆あなたの明るく、元気な、笑顔の為に、ミルキーハウスは前進します!
未来の夢を繋げ精神性の絆の為に創造への意識へとシフトチェンジします!
